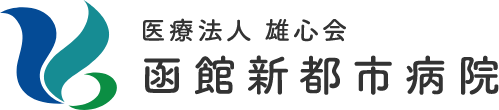片頭痛
片頭痛
疾患概要
片頭痛は、ズキズキと脈打つような頭痛が繰り返し起こる病気です。脳の検査を行っても異常が見つからないことが特徴で、15歳以上の頭痛持ちの約8.4%が片頭痛と診断されています。特に10~50歳の女性に多く見られる疾患で、日常生活に支障をきたすこともあります。
原因・症状
片頭痛の発生メカニズムは完全には解明されていませんが、脳の血管の収縮と拡張、または三叉神経が関与する「痛み物質」の放出が関係していると考えられています。ストレス、ホルモン変動、睡眠不足、特定の食品(チョコレートや赤ワインなど)が誘因となることがあります。
症状には、以下の2つのタイプがあります。
-
前兆のない片頭痛:ズキズキとした拍動性の頭痛が数時間から3日間続き、片側に発生することが多いが、両側に現れることもあります。日常的な動作で悪化し、吐き気、嘔吐、光や音への過敏症を伴うことが特徴です。
-
前兆のある片頭痛:頭痛が発生する前に視野が欠ける(半盲)、ギザギザの光が見える(閃輝暗点)といった症状が現れます。これらの前兆は4分から60分間持続し、その後に片頭痛が始まります。
検査
片頭痛の診断には、問診と頭痛の頻度・症状の確認が重要です。CTやMRI検査では異常が見られないことが多いため、他の疾患(脳腫瘍や脳出血)との鑑別のために行われることがあります。診断基準として、拍動性の痛みや発作の繰り返しが5回以上あることが考慮されます。
治療
頭痛発作時の対処
発作時は、暗く静かな場所で安静にし、光や音の刺激を避けることが有効です。冷却シートや冷たいタオルで患部を冷やすと痛みが和らぐ場合もあります。
薬物療法
-
鎮痛薬:軽度の片頭痛には、市販の鎮痛薬(アセトアミノフェンやイブプロフェン)が有効です。
-
トリプタン製剤:強い頭痛には、血管の異常な拡張を抑え、痛み物質の放出を防ぐトリプタン製剤が効果的です。現在、日本では5種類が利用可能で、60%以上の患者に有効とされています。
-
予防薬:発作の頻度が高い場合には、カルシウム拮抗薬(塩酸ロメリジン)や抗てんかん薬(バルプロ酸)などが処方されることがあります。
予防のポイント
片頭痛を予防するためには、以下の生活習慣の改善が重要です。
-
-
規則正しい睡眠をとる(睡眠不足や過眠を避ける)。
-
食事を抜かず、空腹を避ける。
-
ストレスを適切に管理する。
-
片頭痛を引き起こす食品(チョコレートや赤ワインなど)を避ける。
-
日差しの強い場所ではサングラスを着用する。
-
片頭痛は命に関わる病気ではありませんが、適切な対処と治療によって生活の質を向上させることが可能です。頭痛の頻度が増えたり、症状が重くなったりした場合は、医療機関を受診しましょう。
対象の診療科
疾患症状ガイド