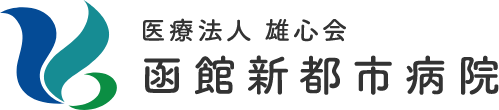てんかん
てんかん
疾患概要
てんかんとは、脳の神経細胞が一時的に過剰な電気的興奮を起こし、繰り返し発作を引き起こす病気です。発作の種類や症状はさまざまで、軽度の意識消失から全身のけいれんまで多岐にわたります。乳幼児から高齢者まであらゆる年代で発症する可能性があり、原因が特定できない場合と、脳の病変や疾患に起因する場合に大別されます。
原因・症状
原因
てんかんの原因は多様で、遺伝的要因が関与するものや、脳の外傷・脳卒中・脳腫瘍・アルツハイマー病などの病気によって発症するものがあります。特に高齢者では脳卒中や認知症に伴って発症することが多い一方、乳幼児や小児では原因が特定できないケースが多く見られます。
症状
てんかんの発作は、発症部位や異常興奮の広がり方によって異なります。主に以下の2つに分類されます。
- 全般発作:脳全体に異常興奮が広がり、意識を失ったり、全身がけいれんしたりする。
- 焦点性発作:脳の特定の部位から始まり、手足のけいれん、視覚異常、短時間の意識消失などが現れる。
特に高齢者では、短時間ぼんやりしたり、記憶が抜け落ちたりする発作が多く、認知症と誤認されることもあります。
検査
-
脳波検査:脳の電気活動を記録し、異常な波形を確認。
-
画像検査(MRI・CT):脳の病変や構造異常を特定。
-
血液検査:低血糖や電解質異常など、てんかんと似た症状を示す疾患を除外。
治療
-
薬物療法
-
てんかんの治療の基本は抗てんかん薬の内服で、多くの患者は適切な薬を継続することで発作を抑えられます。
-
しかし、一部の患者では薬剤が効きにくい「薬剤抵抗性てんかん」があり、他の治療が必要となる場合があります。
-
-
外科治療
-
焦点切除術:発作の起点となる脳の一部を切除し、発作の発生を防ぐ。
-
迷走神経刺激療法:頸部の迷走神経に電極を装着し、電気刺激を与えることで発作を軽減。
-
-
食事療法
-
ケトン食療法:糖質を制限し脂質中心の食事を取ることで、発作を抑える効果が期待される。
-
-
ホルモン療法
-
小児のウェスト症候群など特定のタイプに対して、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)を用いた治療が行われる。
-
多くの患者は適切な治療により発作をコントロールでき、通常の社会生活を送ることが可能です。症状の種類や重症度に応じて、適切な治療法を選択することが重要です。
対象の診療科
疾患症状ガイド