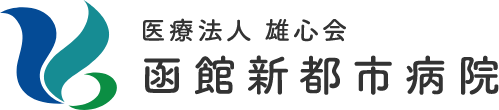パーキンソン病
パーキンソン病
疾患概要
パーキンソン病は、脳内の神経伝達物質であるドパミンが不足することで、手足のふるえ(振戦)、動作の遅れ(動作緩慢)、筋肉のこわばり(筋強剛)、バランスを崩しやすくなる(姿勢反射障害)といった運動症状が現れる病気です。高齢になるほど発症リスクが高まり、日本では1,000人に1~1.5人の割合で発症するとされています。50歳以上の発症が多いですが、40歳以下で発症する若年性パーキンソン病もあります。
原因・症状
原因
パーキンソン病は、脳の黒質と呼ばれる部分にあるドパミン神経細胞が減少することで発症します。なぜ減少するのかは完全には解明されていませんが、αシヌクレインというタンパク質の異常な蓄積が関与していると考えられています。また、遺伝的要因が関与する場合もありますが、大半は遺伝性ではありません。
症状
-
運動症状: ふるえ(安静時振戦)、筋肉のこわばり(筋強剛)、動作が遅くなる(動作緩慢)、姿勢を保ちにくくなる(姿勢反射障害)
-
非運動症状: 便秘や頻尿などの自律神経障害、うつ症状や認知機能の低下、嗅覚障害、睡眠障害、疲労感や疼痛などが見られます。
検査
パーキンソン病の診断は、特徴的な運動症状の有無を確認し、類似疾患を除外することで行います。主な診断基準には、ドパミン補充療法への反応や、CT・MRIなどの画像検査による他の疾患の除外が含まれます。また、DATスキャンと呼ばれる核医学検査を用いることで、ドパミン神経の機能低下をより詳細に評価できます。
治療
-
現在のところ、パーキンソン病を完治させる治療法はありませんが、症状を軽減し生活の質を向上させる治療が行われます。
-
薬物治療: ドパミンを補う「レボドパ」、ドパミンの働きを助ける「ドパミンアゴニスト」、分解を抑える「MAO-B阻害薬」「COMT阻害薬」などが用いられます。
-
手術療法: 脳深部刺激療法(DBS)という手術が行われることがあり、脳に電極を埋め込み、特定の部位を刺激することで症状を改善します。
-
リハビリテーション: 運動機能の維持・改善を目的とし、理学療法や作業療法を併用することが有効です。
パーキンソン病は進行性の疾患ですが、適切な治療とリハビリにより、長期間にわたり生活の質を維持することが可能です。定期的な運動やバランスの取れた食生活、医療従事者との連携が重要です。また、転倒を防ぐための住環境の工夫や、日常生活のサポート体制を整えることも大切です。
-
対象の診療科
疾患症状ガイド